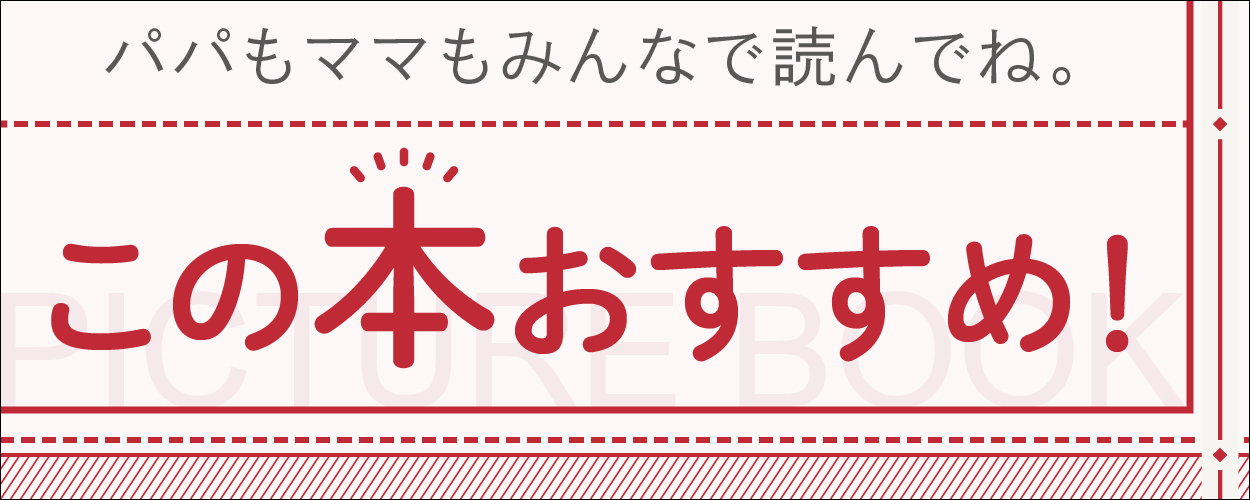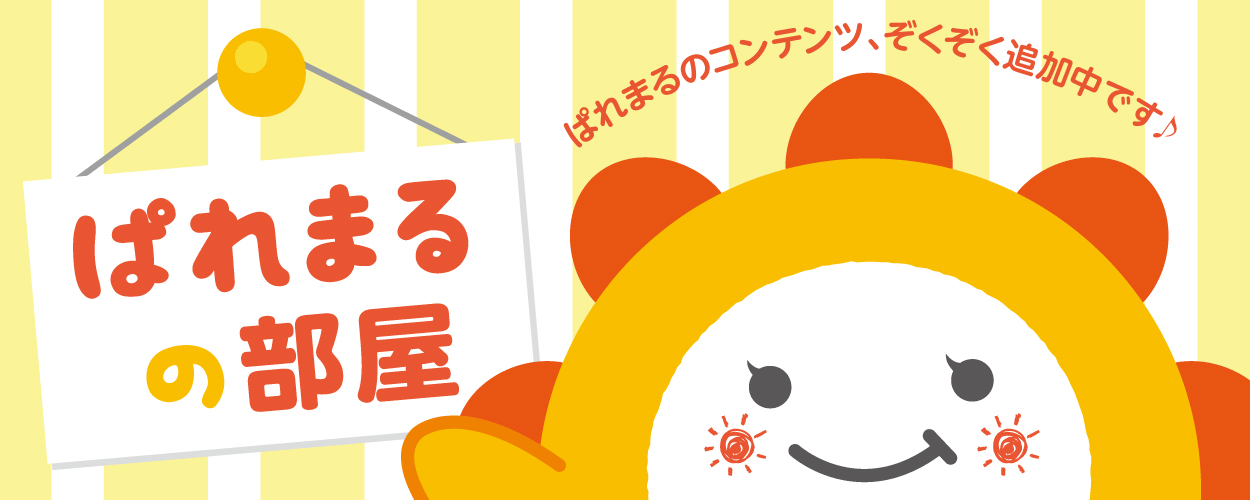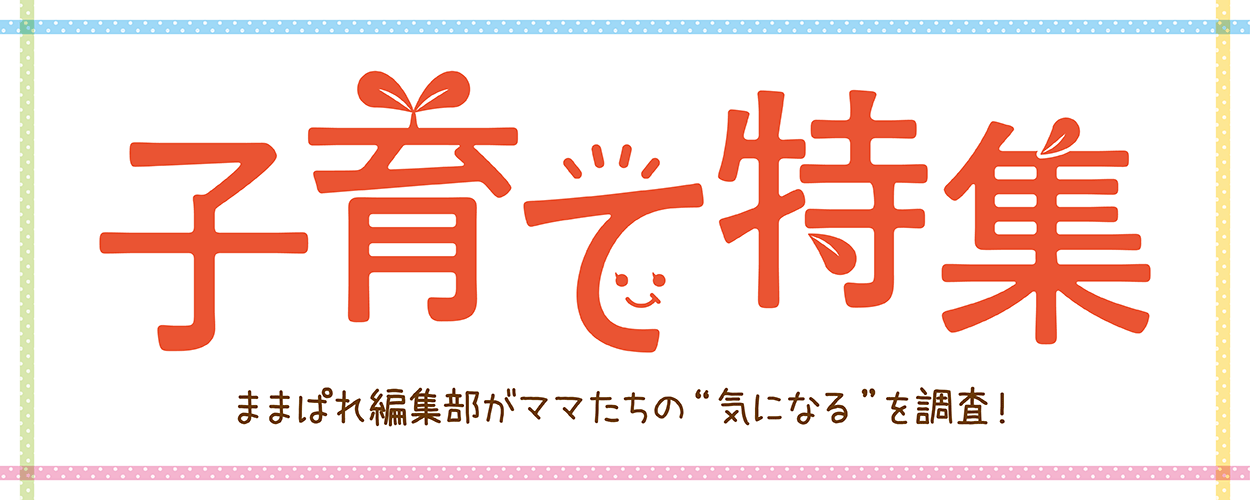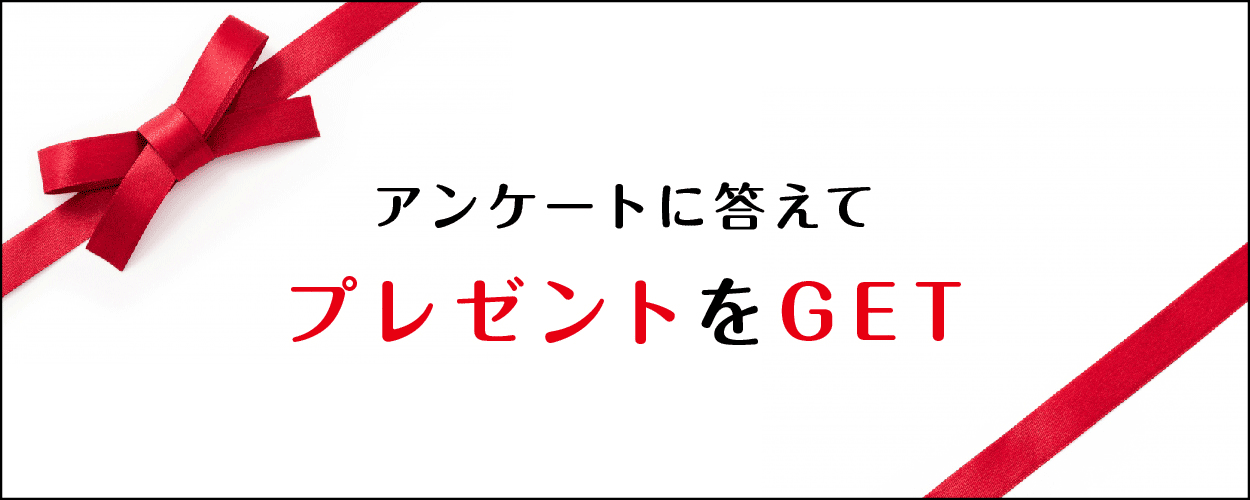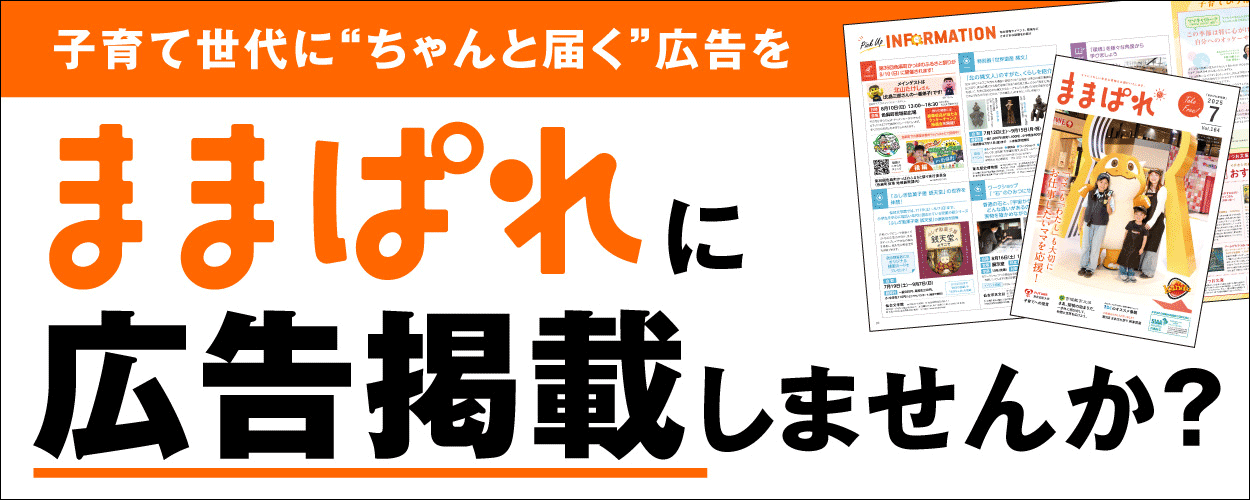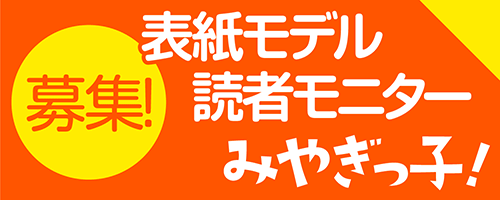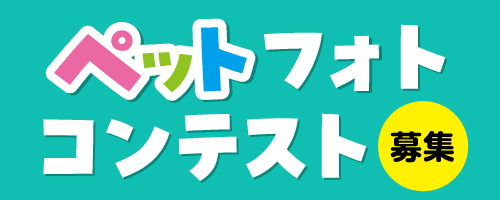宿題をだらだらやる娘にイライラ…親はどう関わる?
この4月に娘が小学1年生になりました。私も初めての小学生のママです。宿題をだらだらやっていたり、ギリギリになってからやるのでイライラしてしまうのですが、どの程度干渉していいのでしょうか?口うるさく言わないで、「宿題したの?」くらいがいいのでしょうか?(仙台市・Sさん)

お子様のご入学、おめでとうございます。真新しいランドセルを背負った背中が頼もしく見える反面、急にお子さんの世界が広くなり、Sさんとしては新しい出来事への戸惑いや不安も抱えておられるのではないかと思います。
宿題をだらだらやっていたり、ギリギリになってからやり始めたりする姿は、はたから見ると「さっさと済ませれば良いのに」と気をもんでしまいますよね。ただ、お子さんも少なからず緊張しながら新しい生活に慣れようとしている分、つい、家に帰ってくると安心して、気持ちも体ものんびりしたくなってしまうのかもしれません。そのため、「宿題は終わったの?」「早くやらないと」といった「させる」言葉がけより先に、「今日も一日疲れたね」「元気に学校行けたね」など、その日のお子さんの頑張りを認めたり、ねぎらったりする言葉をかけてみてください。
学校の宿題に関しては、小学生とはいえ、お子さんはまだ1年生ですので、親御さんの声がけや見守りが大切です。学習習慣をこれから身につけていく段階ですので、「そろそろ宿題を始めようか」、「今日はどんな宿題が出たの」など、宿題を始めるための声がけ、内容を確認するための声がけなどをすると良いでしょう。また、可能であればSさんがお子さんのそばについて見守ることも、1年生のうちは過干渉すぎることはありません。お子さんがその日学校で教わってきたことを尋ねたり、覚えてきたこと、学習してきたことを認める言葉をかけたりすることで、学ぶ楽しさを共有することを心がけてみましょう。
宿題がだらだら、ギリギリになってしまわないためには、お子さんと一緒に宿題をするルールを決めてみましょう。この時、大人が一方的にルールを決めてしまうと、「させられている」印象が強くなり、自分でルールを守ろうという気持ちが薄くなってしまいます。そのため、あくまでもこのルールは、お子さんと一緒に、お子さんの意見を聴きながら決めることが大切です。とはいえ、突然「ルールを決めましょう」と言われても、なぜルールが必要なのか、どのようなルールが必要なのか、お子さんもまだ十分わからないお年頃かと思います。そのため、ルールを決めておくとどのような良いことがあるのか(例えば、「宿題をしてから遊ぶ」と、さっさと宿題を終わらせた分、たっぷり遊ぶ時間がとれる、など)を、ルールの大切さとあわせて説明してみてください。また、大人目線で「守らせる」ためのルールではなく、お子さんが「守れそうな」ルールから決めてみましょう。最初から大人目線で「できて当たり前」と思われるルールを設定してしまうと、お子さんがそれをなかなか守れなかった場合、「ルールなんて決めても意味がない」、「どうせできない」、「もうしばられたくない」といったネガティブな方向に意識が向いてしまう可能性があります。そのため、まずはお子さんが守れそうなところから、スモールステップでルールを設定してみましょう。さらに、ルールを決めたら紙に書き、お子さんが見えるところに貼るなど「見える化」することで、ルールの確認や意識づけを促すことにつながります。
また、「やりなさい」だけでは益々お子さんの気持ちが後ろ向きになってしまいます。大人でも、ついやりたくないことは後回しにしてしまったりすることがあることを思い出しながら、「やらなきゃいけないとわかっていても、なかなか気が進まないこともあるよね」など、お子さんの気持ちに共感を示しつつ、「そろそろ始めようか」、「もう少しスピードアップしてみようか」などと、提案してみましょう。
とはいえ、毎日のこととなると、穏やかにお子さんの宿題を見守り続けることはなかなか難しいことだと思います。根気がいることと思いますが、小さなことでもお子さんができた時、変われた時は、それを認める言葉がけをしながら、焦らずにお子さんの成長を見守ってみてください。
POINT!
お子さんがその日学校で教わってきたことを尋ねたり、覚えてきたこと、学習してきたことを認める言葉をかけたりすることで、学ぶ楽しさを共有することを心がけてみましょう。
アドバイスをいただいたのは…
高野 亜紀子先生
青森県出身。専門は子ども学。社会福祉士。
現東北福祉大学総合福祉学部准教授。
2児の母としての経験を生かしながら、子育て支援、保護者支援、保育者養成に関する実践・研究活動を行っている。
子育ての悩みを相談したい方はこちらから