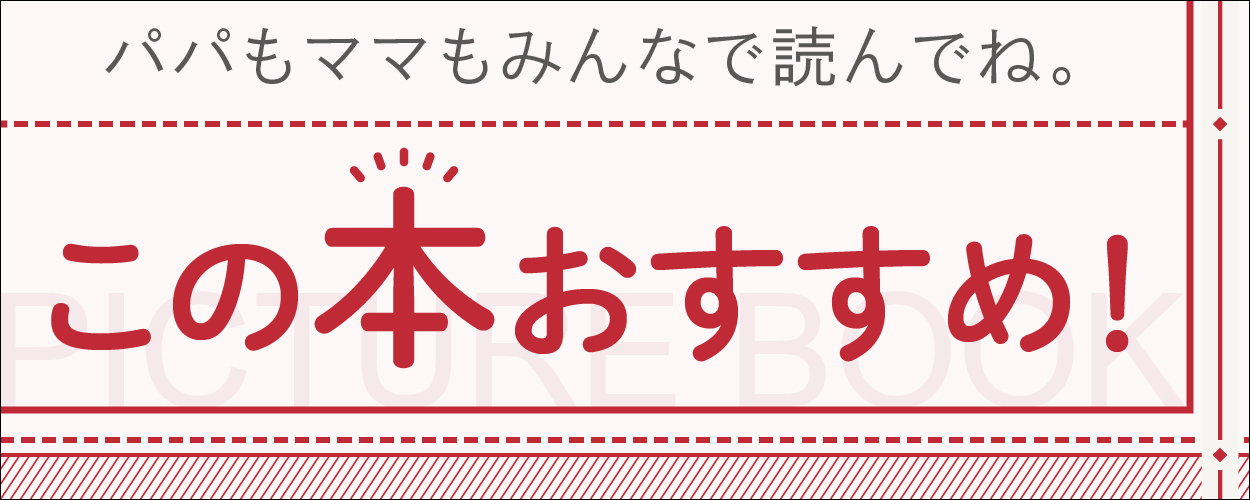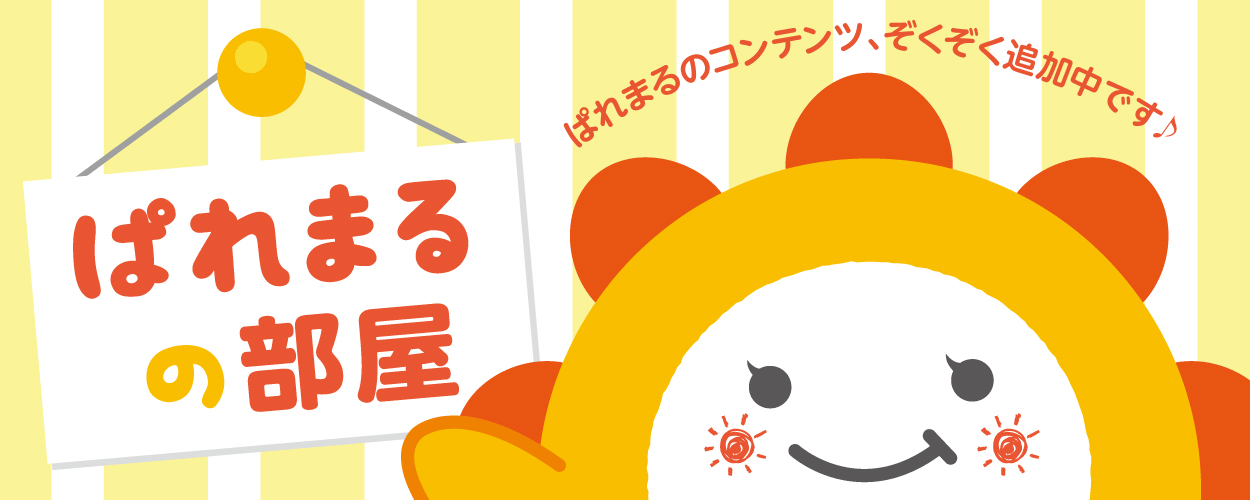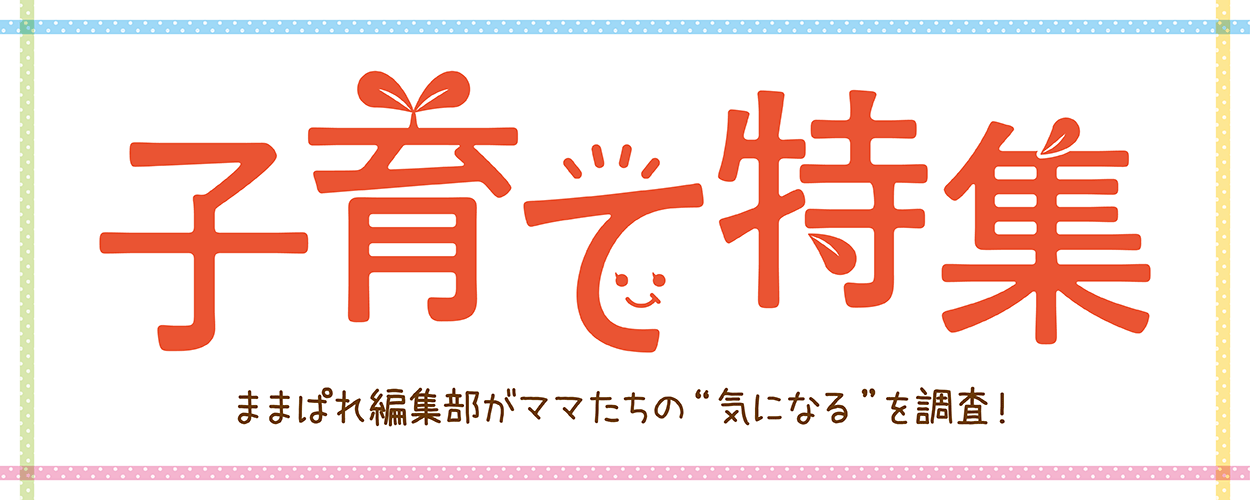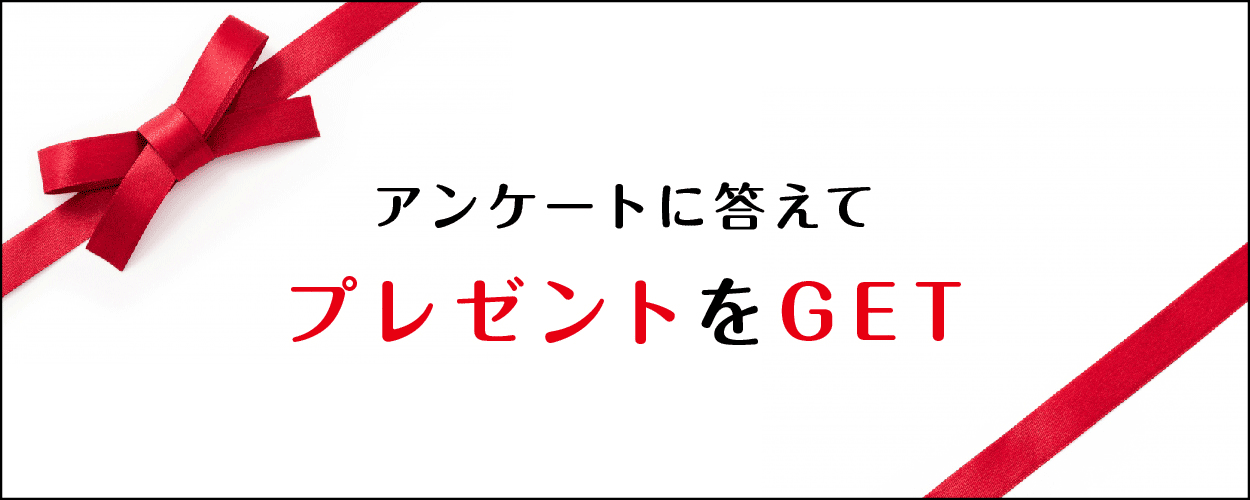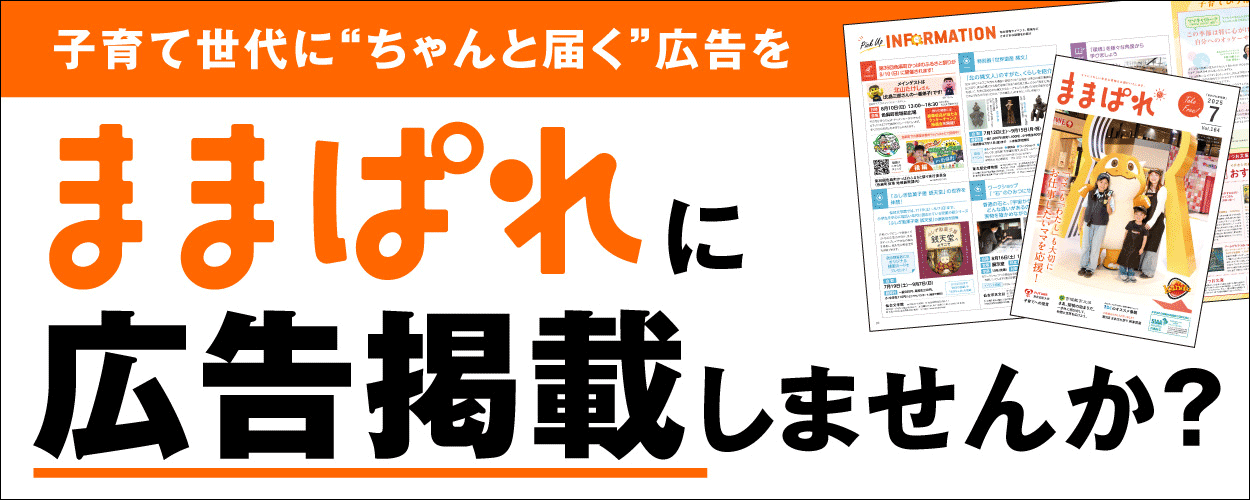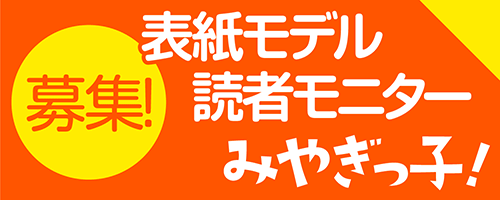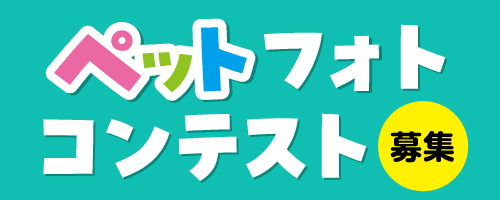特集 デジタルメディアとの付き合い方
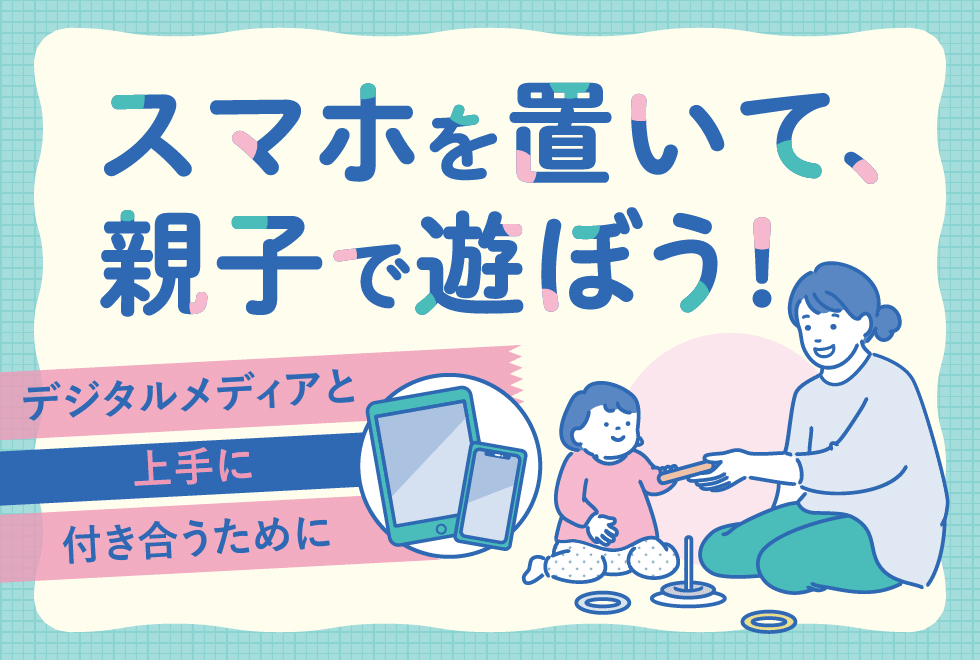
みんなもやっているから…と、
子どもがぐずったらスマホでYouTubeを見せていませんか?
近年はデジタルメディアの影響で、それまで見られなかった異常行動を抱える子どもが増えています。
乳幼児期からの長時間のデジタルメディア視聴が及ぼす影響と、その改善方法を考えます。
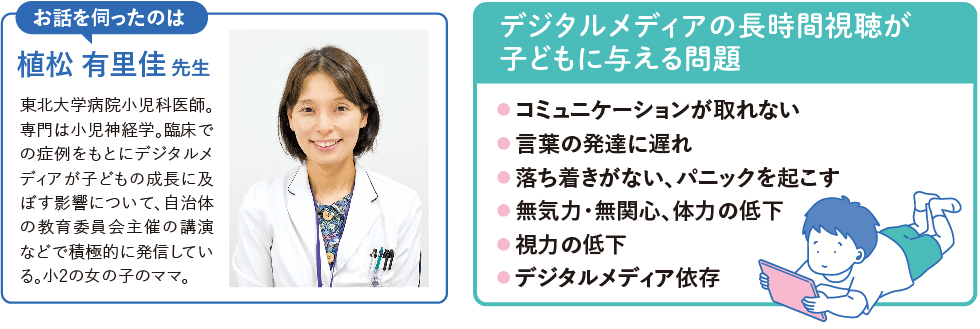
デジタルメディアの長時間視聴が子どもに与える問題
- コミュニケーションが取れない
- 言葉の発達に遅れ
- 落ち着きがない、パニックを起こす
- 無気力・無関心、体力の低下
- 視力の低下
- デジタルメディア依存
愛着を形成する一番重要な時間が失われている?
外来で発達障害のお子さんも診ていますが、この5年ほどで大きく変化してきたことがデジタルメディアの影響だと思います。小児科での診療は子育て支援的な要素が大きく、小さい時の生活習慣をかなり徹底して行っています。これまでは「早寝・早起き・朝ごはん」でしたが、それにデジタルメディアの管理が加わりました。
乳幼児期は、人が愛着を形成するために最も重要な時期です。赤ちゃんは泣くことで授乳してもらったり、抱き上げてあやしてもらったりしながら、保護者と絶対的な信頼関係を築き、愛着を形成します。「愛着」とは対人関係の基礎であり、人を信用して行動する能力のことで、1歳の誕生日頃までが愛着形成に最も重要な時期です。愛着が形成されてこそ、躾や様々な社会的ルールを学ぶことができ、その次に親御さんとの絆に支えらえながら、友だちと遊んだり競争したり、仲間との関係を作っていきます。
その愛着が形成されるはずの時期にスマホであやされていたり、子どもが泣いたり何かを訴えても、親のほうがデジタルメディアに気を取られていたら、本来必要な愛着が形成されません。安心感や信頼の土台がない状態でいくら躾をしようとしても身に付きませんし、友だちと仲良くしたり、ルールを守って遊ぶこともできず、発達障害が疑われるようになります。デジタルメディアそのものが悪いというより、本来愛着を作る一番重要な時間や親子のやり取りが、デジタルメディア視聴に取って代わってしまうことが影響していると私は考えています。
「ちょっと変?」が表面化するのは4歳を過ぎてから
親子のやり取りは、お子さんの言葉を育みます。乳幼児はだいたい1歳~1歳半までの間に言葉が出てきますが、それまでにも話しかけてもらったり、会話を聞くことで言葉を受け取っています。「あー」や「うー」といった言葉にならない喃語※も、お母さんがきちんとキャッチして、反応してくれることで言葉が育っていきます。
しかし、家のテレビなどが点いていると、本人の声を保護者がキャッチできなくなり、保護者の声も子どもに届きにくくなってしまいます。最近は乳幼児でも自分でスマホを見ている時間が2時間を超え、自宅のテレビはつけっぱなしというご家庭も多くあります。その時点では深刻な事態は表面化していませんが、4歳を過ぎた頃から「言葉がほかの子 に比べて遅い」「ちょっと複雑なやり取りのある遊びが難しい」 「ルールを守って遊べない」など、コミュニケーションや協調性が取れていないことに気づかれることがあります。
ですからお子さんが小さいうちに、親御さんたちにはこの問題に気づいてほしいと思っています。
このほかの症状としては、言語発達の遅れに伴い、気に入らないことがあっても言葉で訴えられないため癇癪やパニックを起こす異常行動。動画やゲームなどの受け身の楽しみにハマってしまったため、自ら関心を持って探索したり、興味のあるものを求めなくなる無気力、無関心。視力の異常や体力の低下なども起こってきます。
※赤ちゃんが意味のある言葉を話せるようになる前の段階でよく見られる特有の音声のこと。
「寝る子は育つ」は本当。まずはここから頑張ってみましょう。
デジタルメディアの視聴時間が長いことは、睡眠時間にも大きく影響します。National Sleep Foundationという国際組織が出している「年齢別に推奨される睡眠時間」による睡眠時間の目安は、1~2歳が11~14時間、3~5歳が10~13時間、6~13歳が9~11時間(乳幼児は昼寝も合計した時間)です。睡眠不足になるとイライラしたり、キレやすくなったり、無気力や落ち着きがないなど心身両面の発達に影響します。十分な睡眠時間を取るだけでも症状はかなり改善されますし、就寝時間を早くすることだけでも頑張れば、結果的にゲームやデジタルメディアに接する時間が減りますので、睡眠時間の確保には力を入れてほしいですね。
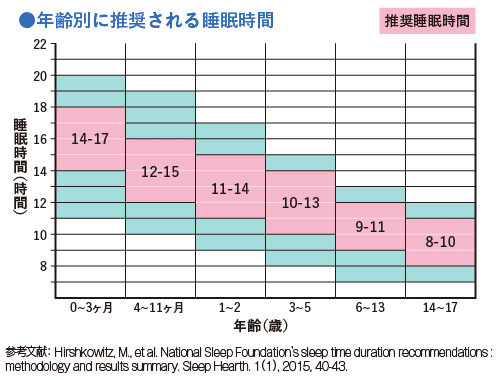
身体を使った遊びで愛着形成を再構築
子どものデジタルメディアの視聴時間の目安は、日本小児科医会が設けている基準では、やはり2歳までの時期は言語と体の発達に重要な時期なのでできる限り控えていただき、2歳以上も2時間以内 (ゲームは30分以内)となっています。ただ、3歳や4歳の子は時間の概念がないので、いつも5時間見ているのを2時間にするのはとても困難です。減らすのではなく、デジタルメディアに費やしていた時間を親子で身体を使って遊ぶことに置き換え、家族で外遊びや自然に親しむ遊びをしたりして、親子で全くデジタルメディアに触れずに3日間過ごしてみてください。連休を使うことはおすすめです。そうすると、子どもはとても満足して、デジタルメディアよりも遊びのほうに集中できるようになります。
2歳以上でも見ないに越したことはないのですが、小学校学齢以上になるとデジタルメディアと上手に付き合うことが必要になってきます。その時には視聴する時間などのルールを決め、子どもたちがどんなものを見て、どんなゲームをやっているか把握しておくようにしてください。最近ではオンラインゲームなどもあり個人で取り組むことが難しくなっているため、比較的小さい自治体では教育委員会や学校を挙げて取り組んでいるところもあります。
また食事の時間も、半分以上のご家庭でテレビやYouTubeが点いているようですが、食事は家族のコミュニケーションの時間で
す。親御さんが作ったものを味わい、今日あったことなどを話したりする時間ですから、デジタルメディアを消してその時間を楽しんでいただきたいと思います。
早寝・早起きの習慣を。子どもは驚くほど変わります。
一緒に遊ぶことと、早寝・早起きの習慣付けに力を入れれば、おのずとデジタルメディアを見る時間は減っていきますから、そこからトライしてみてください。大人と違い、子どもは驚くほど早く改善します。もちろん本気で取り組まないと大変ですが、間違いなく変わります。
私にも小2の娘がいますが、人と関わることが好きな、その喜びや楽しみを感じられる人になってほしいなと思っています。また、早寝・早起き・朝ごはんの習慣は後から獲得できないので、親が子どもにしてあげられるプレゼントではないかと思っています。病院の外来に来て、見違えるように回復した子どもたちもたくさんいます。私たちもお母さんたちを応援していきますので、子育てを楽しみましょう。