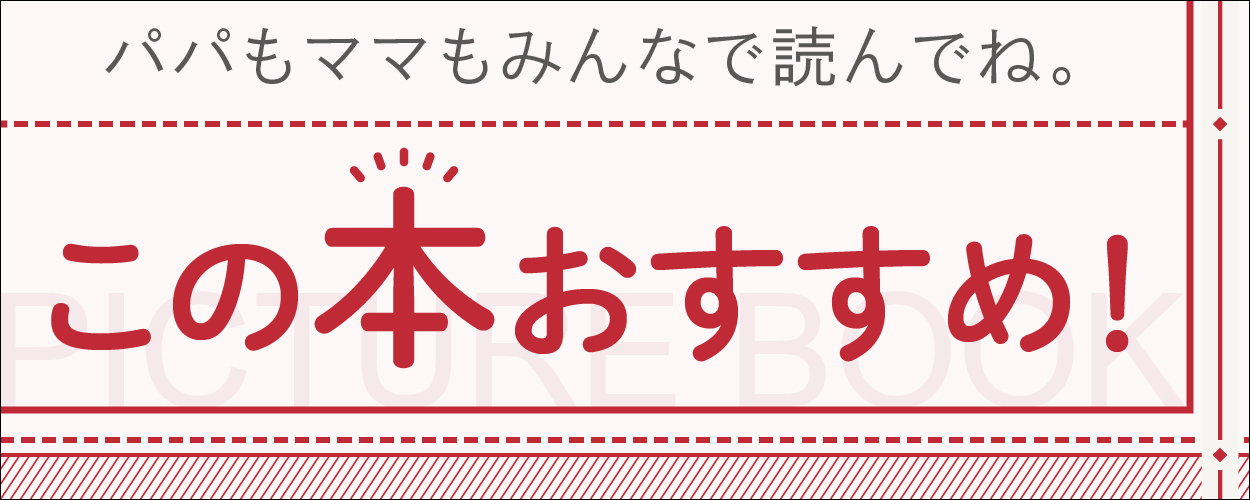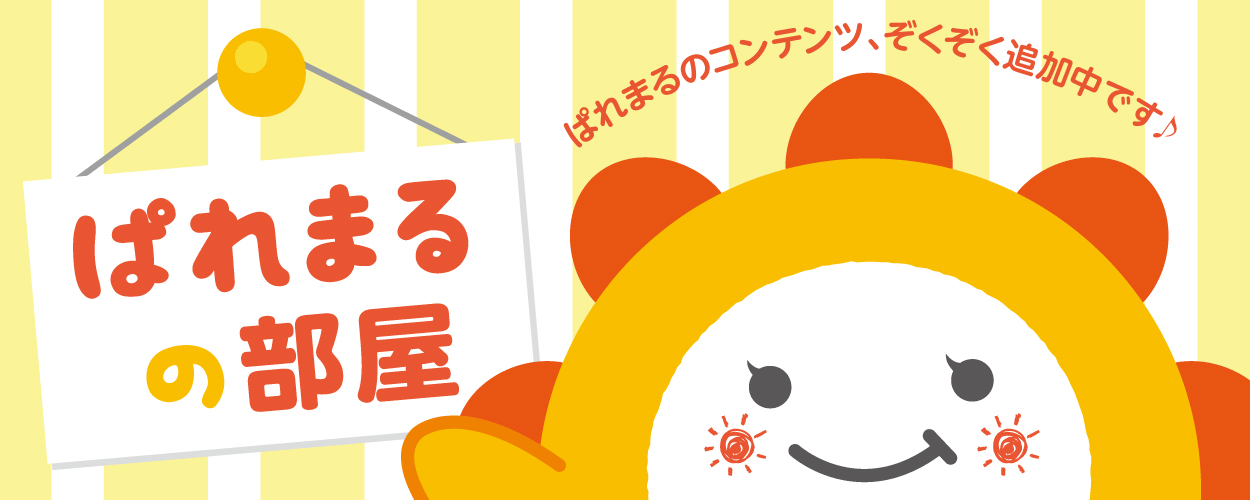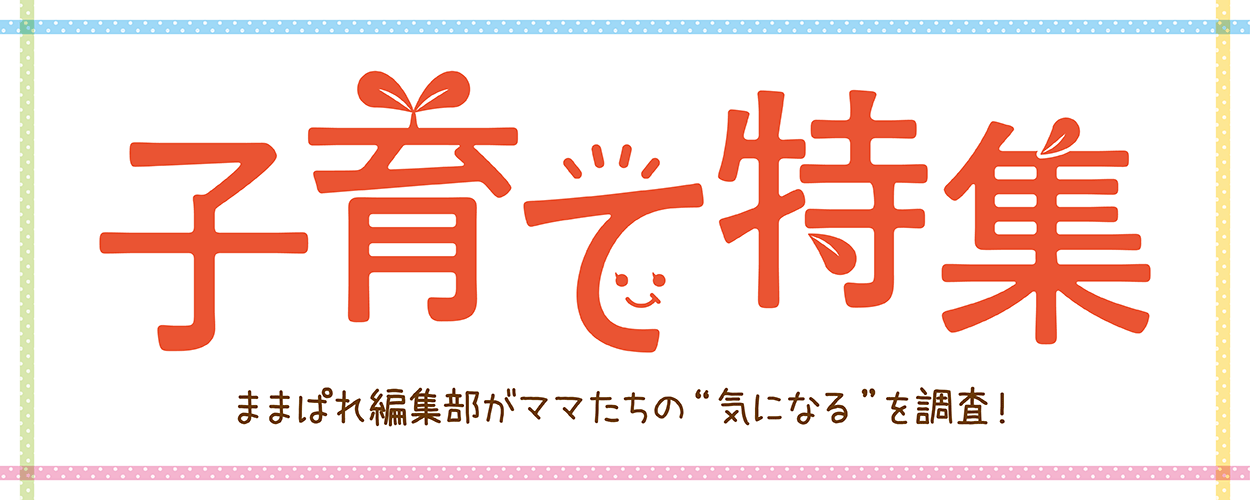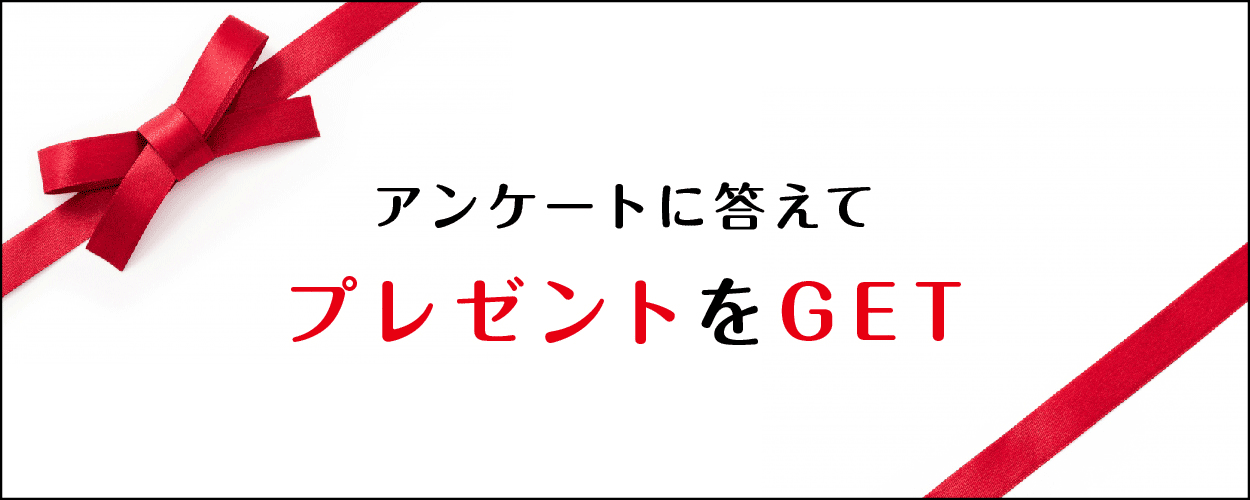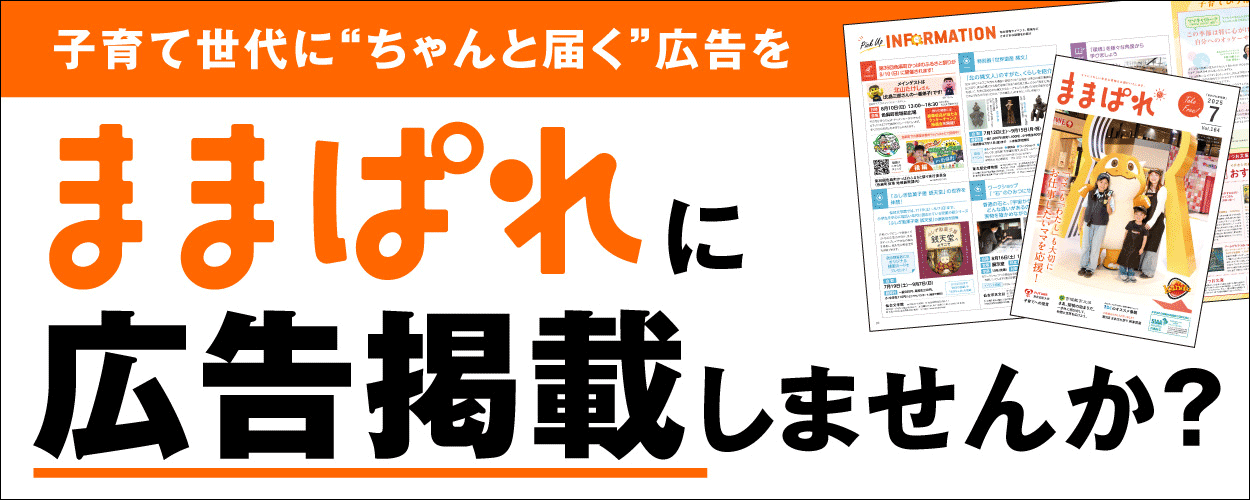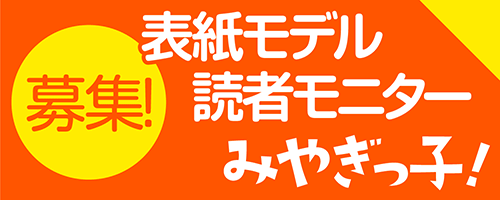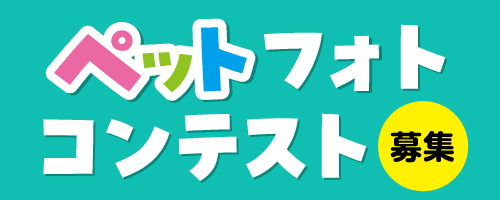地形から災害の備えを考えよう!
大規模な山火事に、自分の街は揺れないのに津波警報が飛び込んできたり、雨が降らずにダムの貯水率が0%になったかと思えば、今度は警報級の大雨―自然相手に手加減を望むのはちょっと難しそうです。ならば効率よく備えよう!ということで、今月は自然環境から防災にアプローチ。
何が危険なのかが分かっていれば、災害に対して合理的・効率的に対処できます。
先生のご専門について教えてください。
私の専門の地形学は、学校では社会科地理でも学びますが、基本的には地球惑星科学(理科)の一分野で、地球表面の凹凸の形や構成物質の特徴、その形成に関するプロセスや歴史を研究する学問です。地形の変化プロセスが災害を引き起こすので、災害科学にも深く関わっています。
私の環境防災研究室では、防災を環境から考える研究と教育に取り組んでいます。災害が起こる原因(環境)が分からなければ対策の焦点が絞れませんが、地形や様々な自然現象を理解することで、より効果的で効率的な減災防災ができるようになります。例えば自分が暮らしている地域が沿岸部だったり、川が山から運んできた土砂が堆積してできた扇状地だったりすれば、過去に津波や洪水・土石流が起こった歴史がある可能性があり、それを意識するだけでも防災に関する見方が変わると思います。
大学ではどのような授業を。
学校防災の講義のほかに、311ゼミナール(※1)を共同で担当しています。今年は学部生と教職大学院生合わせて54名が登録しています。311自体に興味がある学生もいますが、震災当時はまだ幼く、内陸や日本海側で暮らしていたなど様々な学生がいますので、今年度からは環境防災班を立ち上げ、そこではより幅広く災害について学んでいます。今年度は2008年に起きた岩手・宮城内陸地震を契機に作られた栗駒山麓ジオパークに聞き取り調査に行くことになっています。
311ゼミで英字新聞の輪読会を企画し、7月にアメリカのテキサス州で起きた大規模洪水と、世界各地で頻発するようになった林野火災の記事を夏休み明けから読むことにしています。テキサスの洪水ではサマー・キャンプに来ていた子どもたちが犠牲になりましたが、キャンプが学校活動の一環で実施される場合もあり、宮教大の学生とそのことを考えてみようと思います。また、林野火災は、植物(主として樹木)が吸収して植物体内に固定化していた二酸化炭素が大気中へ放出される現象であって、その放出量は今や地球温暖化に影響するレベルになっていることが書かれており、環境と災害(防災)は不可分であることの一例が科学の視点から端的に示されています。このような世界各地の様々な災害の記事には日本にいては見えにくい視点が含まれています。
将来先生になる学生さんたちにとって、防災の学びは大切ですね。
地震はもちろんですが、最近は雷や雹(ひょう)、竜巻など極端気象による災害が学校現場に大きく影響しています。雷注意報が出れば、子どもたちを帰宅させていいのか、校庭で部活動をやらせていいのかなどの判断にも影響するからです。
附属学校と共同で進める学校防災・防災教育に関する研究として、学校の防災マニュアルの改訂に取り組み始めました。仙台市中心部にある幼稚園、小中学校と、青葉山にある特別支援学校とでは立地環境が異なりますので、想定される災害にも違いが出てくることをマニュアルに入れ込んでいこうと考えています。またそのマニュアルの中身を、もっと教育現場に活かしていければとも思っています。小学校では、地域社会の視点で防災を学ぶ社会科だけでなく、災害の原因となる自然現象を学ぶ理科での連携は有望ですし、中学校では更に英語などとの連携も模索していきたいですね。
災害や防災の専門教育以外にも、時代の違いを超えて普遍的だと思える価値観はきちんと伝えていきたいと思っています。学生たちには、最近の虚々実々な情報に流されることなく、自分なりの視点や軸を持って学び考え、それを子どもたちに教えていって欲しいと思います。
子どもの頃から地理などが好きだったのですか?
旅行や地図が好きで、地図などはずっと見ていられました。海外の様々なことを知るのも好きだったし、知らない土地への好奇心が強かったことが今に繋がっていると思います。地形学の優れた先輩方は子どもの頃から身近な自然や近くの山の地形を「不思議だな」と思い、それが学問に結び付いていった例は少なくないようです。私は東京西郊の武蔵野台地で育ったので、近くに山はないし、川といえば玉川上水でした。そういう環境で育ったことが地形学に取り組むにはハンディだと感じたから、今でも現場に行くことにこだわっているのかもしれません。
私は東北大学での学生時代に、よく荒浜の深沼海水浴場へ行っていました。それから年月を経て、2011年10月に東京農工大学の学生を連れて気仙沼市にボランティアに来た時に荒浜にも行ってみたのですが、その光景にショックを受けました。今は海水浴場が再開しているそうなので、ぜひ行ってみたいと思います。
ままぱれ読者にアドバイスをお願いします。
防災に関していえば、自分が住んでいる場所の危険は何かきちんと理解することだと思います。自治体が作成しているハザードマップを見たり、家族や地域の人達と話して意識を持つことが大切だと思います。何が危険なのかが分かっていれば、危険が迫っているかどうかを自ら判断する取っ掛かりになりますし、危険が迫った際にはどうするか、そのために日頃からどう備えるかなど、災害に対して合理的・効率的に対処できます。
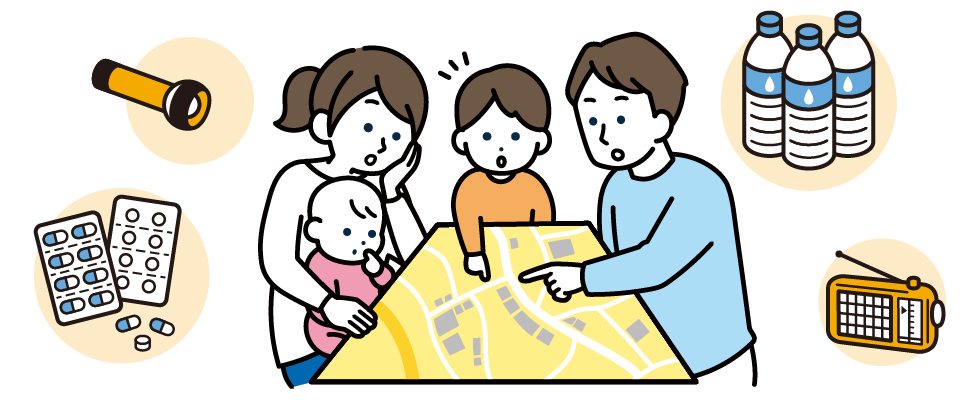
子どもたちに関しては、私はSTEAM教育(※2)のイベントを手伝うことがあり、そこで個別の相談を受けるのですが、「親の期待を裏切りたくなくて、部活をやりたいけれど塾があるからできない。どうしたらいいですか?」と聞かれたことがあります。遺伝子を研究している先生が、「今の子どもはそれぞれの個性に関係なく期待されて、同じように扱われて本当に可哀想だ」とおっしゃっていましたが、私の考えをその子にアドバイスしたら「分かってくれる人がいた」と泣かれ、驚きました。親に対して素直でも、本当は小さい胸を痛めて悩んでいる子たちが身近にもいるのだと思います。
その反面、「子どもに任せている」というような、ほったらかしの教育というのは、私はないと思っています。これはメンタリングと呼ばれるもので、私も経験上、あの時にこうしたアドバイスがあれば人生は変わっていたかもしれないと思ったことがありました。お子さんの声に耳を傾けてお子さんの個性を考え、自分の経験と知識を総動員して、良い方向へと導く助言者になっていただければと思います。
※1 311ゼミナール 防災教育研修機構が運営する学生主体の自主ゼミで、自ら震災に向き合い、避難や伝承など、教師の役割を考える様々な活動を行っている。
※2 STEAM教育 科学(Science)、技術(Technology)、工学(Engineering)、芸術(Arts)、数学(Mathematics)の5つの領域を対象とした理数教育に創造性教育を加えた教育理念。