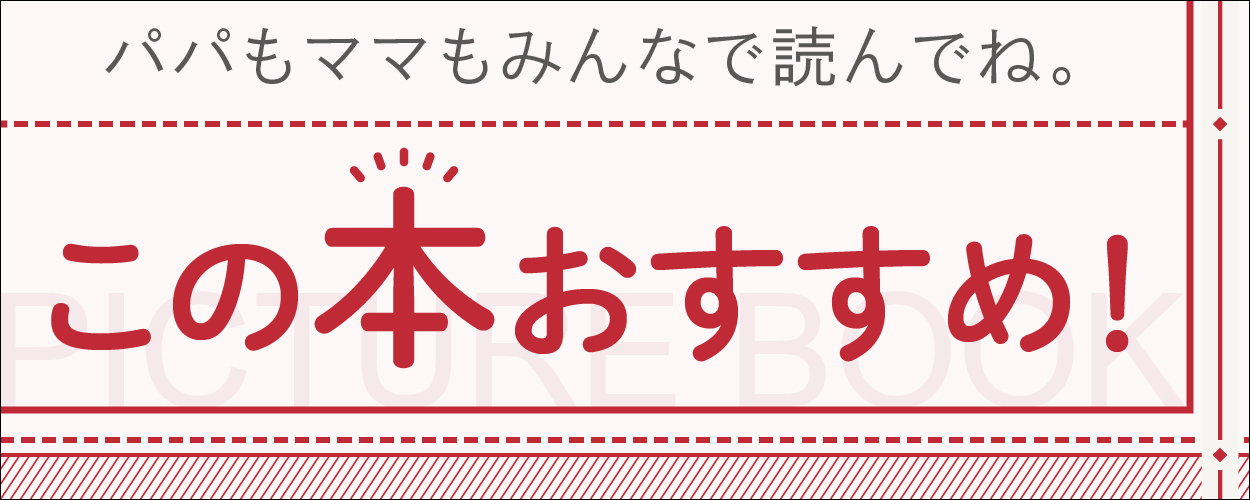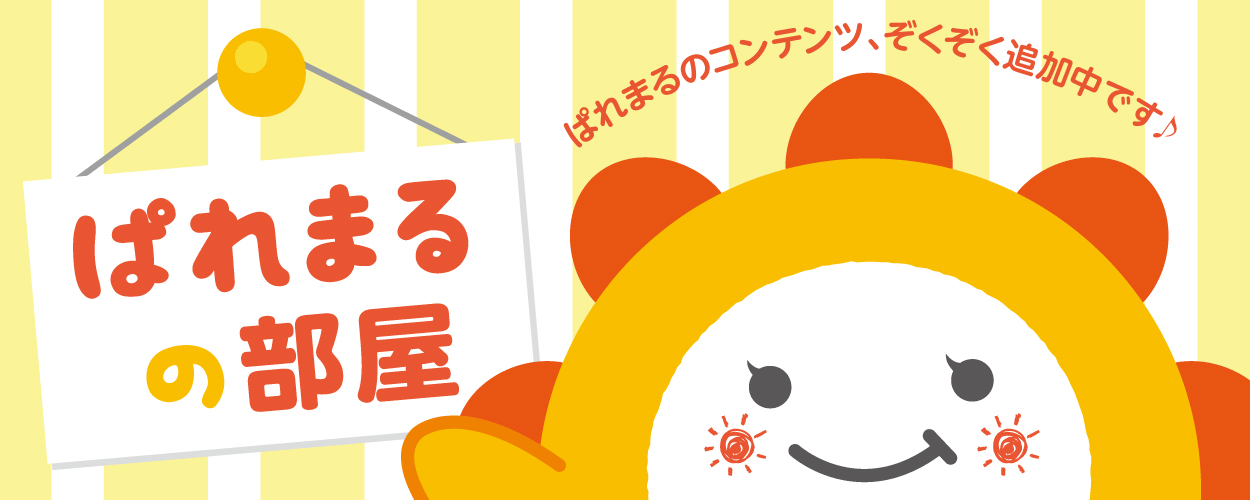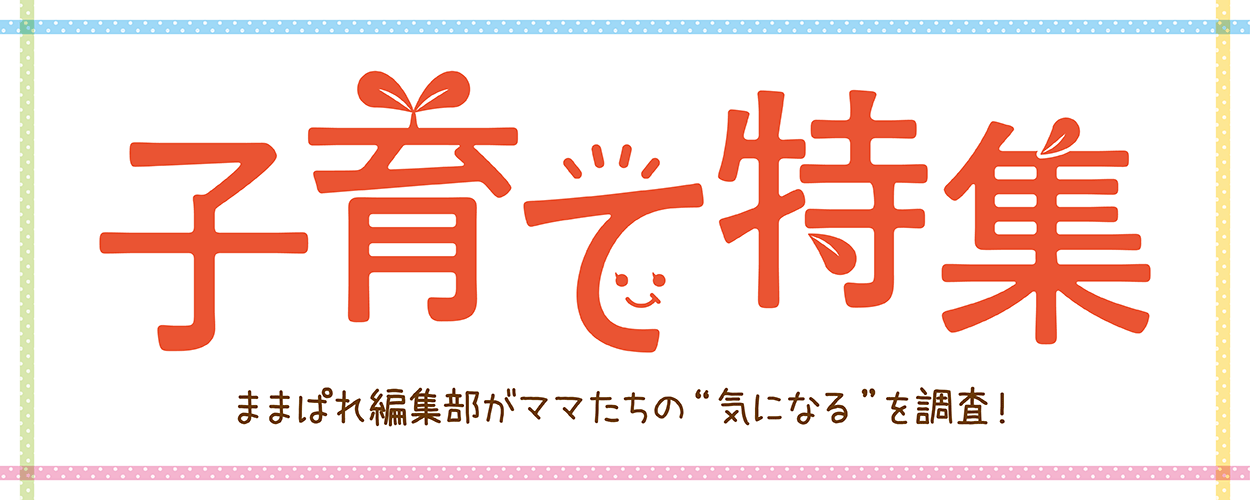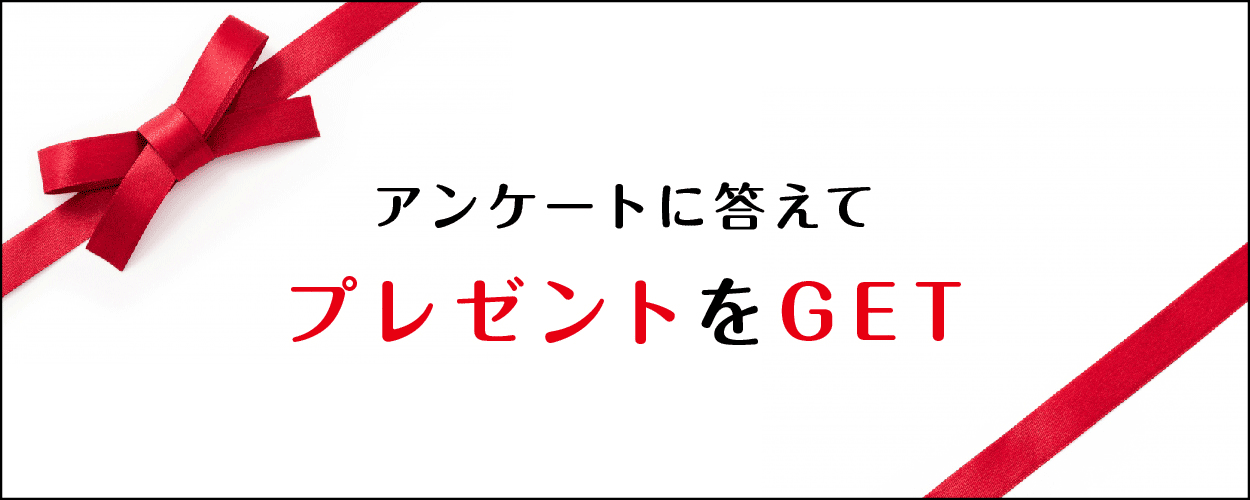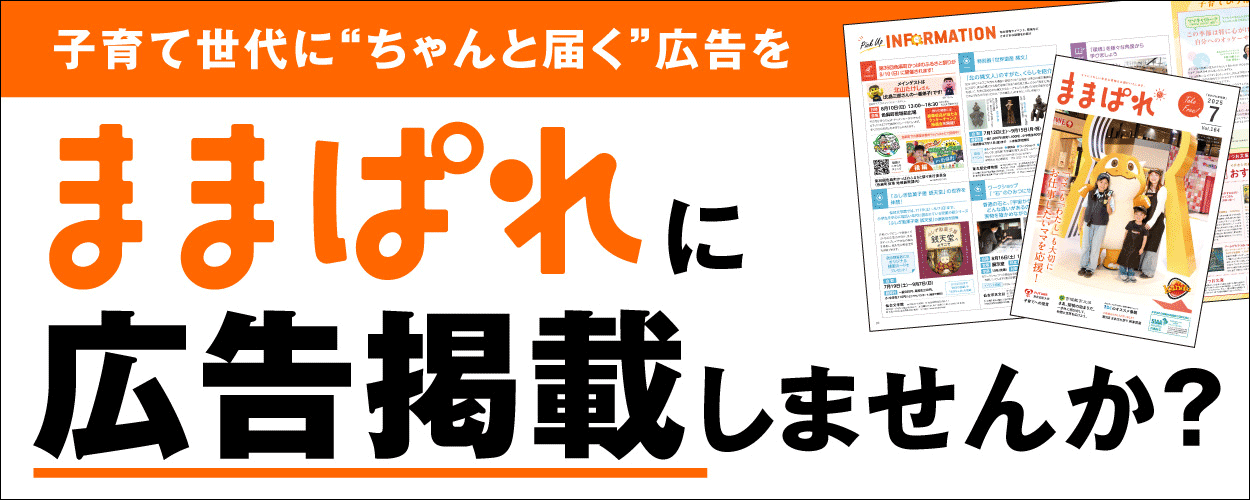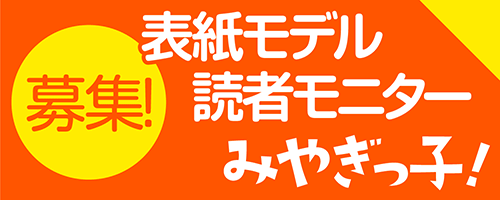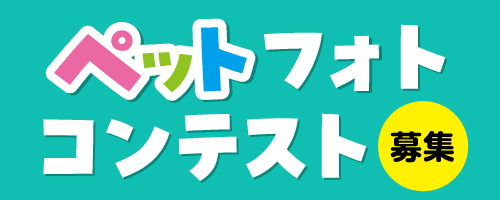子どもの嘘や作り話、どう受け止めればいい?

小学校3年生の息子はよく嘘をついたり作り話をします。
それもその場の言い逃れのような下手な嘘やあからさまな作り話で、ひょっとして虚言癖があるのかとも思うのですが、学校でも同じようなことをして、みんなに嫌われていないか心配です。 どう向き合えばいいでしょうか。
「うそつきはどろぼうのはじまり」という言い回しがあるように、私たちは嘘をつくことは悪いことだ、という暗黙の了解の中で生きています。これは、嘘をつくことがあたりまえだという気持ちになると、道徳的な心も失われていくということだろうと思います。一方で、年齢に関係なく、なにかしらの嘘をつきながら生活しています。それは自分を守るためであったり、相手を傷つけないためであったり、そのほかにも様々な理由のために事実でないことを言ったりします。遊びに誘われて「都合が悪いから残念だけど行けない」とは言いますが、「あなたと遊んでもつまらないから行かない」という「本当のこと」は、トラブルを避けるために言わないものです(笑)。では、子どもたちのつく嘘や作り話はどんな理由があるのでしょうか?
就学前くらいの小さな子どもたちは、感じたものをそのままことばに出すことも多いものですが、小学生くらいになると様々なタイプの嘘をつくようになってくるものです。よくある嘘の一つめは、めんどうなやり取りを避けるための嘘です。「宿題やったの?」という問いかけに、やってないのに「もうやったよ」というような嘘は、本当のことを言ってしまうと、そのあとにめんどうなやり取りが続くことが予想できるからですね(笑)。すぐにバレるということはわかっていても、つい言ってしまうその場しのぎの嘘です。
二つめは、「注目されたい」ためにつく嘘です。小学生になると他の子たちから一目おかれたい、負けたくないという心も出てきていますので、友だちから「夏休みに沖縄に行ってきた」と言われれば、「僕だって北海道行ってきた!」とか、「新しいゲーム機買ってもらった」と言われれば「僕だって持っているよ」と、つい口に出てしまうこともあります。こちらもすぐにバレる嘘や作り話ですが「その瞬間に注目されればそれでいい」という嘘ですね。バレた時に周りの子たちからどう思われるかまでは思いが至りません。
Aさんのお子さんが、誰に対してどのような嘘や作り話をするのかにもよりますが、嘘をつくことに対して強く叱る必要はないように思います。Aさんへの嘘が多いのであれば、「ほんとは宿題おわってないよね?遊んでないで今すぐやりなさい!」ではなく、「あとででもいいから、ちゃんとやってね」であればお子さんは嘘をつく必要はなくなります。また、友だちにつく嘘が多いのであれば、おそらくお子さんはバレたあとに気まずい思いをしながら「もうこういうタイプの嘘をつくのはやめよう…」と学び、「僕だって北海道行ってきた!」ではなく「どこに行っても暑いから、夏はどこにも行かないことにした!」というように、私たち大人もついている、余計なトラブルにならず誰も傷つかない嘘をつけるようになっていくのではないでしょうか。
そのとき、もしかするとAさんが心配なさっているように一時的に他の子から変な目で見られるようなこともあるかもしれません。それを恥ずかしいと感じて、お子さんが自分の力で修正していく力を信じてみてはいかがでしょうか。そして、万が一、嘘によって友だちと大きなトラブルになったり、誰かを傷つけてしまうようなことがあったら、その時にお子さんと嘘について一緒に考え、話し合っていただければと思います。
Point
嘘をつくことに対して強く叱る必要はないように思います。お友だちに注目されるためについた嘘で、一時的に変な目で見られるようなこともあるかもしれませんが、それを恥ずかしいと感じて、お子さんが自分の力で修正していく力を信じてみてはいかがでしょうか。